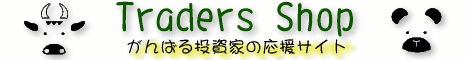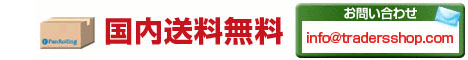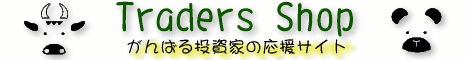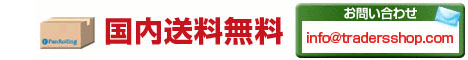気象庁113年の歴史の中で最も暑い夏となった2010年。
横綱・白鵬が双葉山の持つ69連勝を九州場所で塗り替えることになるかもしれない今年、林則行氏の「株の公式」が刊行された。読後の最初の印象は、この本はひょっとしたら株式投資の世界の新しい古典になるかもしれないというものであった。今後、株式投資を志す投資家は、この力作に盛り込まれた知識を糧に、ますます先に進むことになるのだろう。そう思うと誠にうらやましい限りである。
著者は景気の動きとはまったく別の次元で、独自の成長過程を歩む爆発力を持った成長企業を選び出すことを提唱しているが、そのノウハウがほとんどすべてと言ってよいほど詰め込まれている。それがこの本の最大の特色でもある。
たとえば、成長企業は業績が飛躍的に伸びることで株価も大化けするものだが、その際に業績の伸びを見るために決算書を読み解く必要がある。しかし決算書の見方を解説する投資関連書籍は、世の中に数え切れないほど存在する。それらの書籍とこの本との間に明確な境界線が引かれる理由は、この本が企業から発表される決算内容と実際の株価の動きとをきちんと関連づけて説明している点である。
株価の動きとの関連において、公表された決算内容のつかみ方を解説した投資関連書籍はきわめて少ない。ほとんど存在しないと言ってよい。この辺りが著者の真骨頂であり、運用の実務に長けたファンドマネージャーの手腕が存分に発揮されていると言えるだろう。著者はこれらの視点を「株の公式」としてまとめ上げている。株式投資に成功の方程式、公式は存在しない、という先入観、既成事実を打ち破ったという点においても、この本はおおいに賞賛されるべきである。
また本書は、投資対象となる銘柄の見つけ方、「買いの公式」ばかりではなく、撤退の方法、「売りの公式」にも多くのページを割いている。実務に携わるファンドマネージャーが売りのノウハウを明らかにするという点でも、類書には見られない公平な視点として高く評価できる。
ネタばれになってしまうので詳細をここに記すことは憚られるのだが、本書のよいところは列挙するのは実にむずかしい。ただ、私も含めて読者の多くは、各段落の書き出しに目次として使用されている刺激的なキャッチフレーズに惹きつけられるのではないかと思う。そのうちのいくつかを挙げてみると・・・
これらの運用におけるポリシーは、すべて著者のファンドマネージャーとしての経験から導き出されている。それだけに記述内容に迫力がある。本の後半部分(売りに関するパート)に少し難解な部分があったのが惜しい点だが、それは上級レベルの投資家のために用意されたもので、実は筆者の最も訴えたかった核心部分でもあるに違いない。相場の奥の奥まで読者に理解してもらいたいという、著者の比類なき親切心の表れと受け止めることができる。
本書は、プロのファンドマネージャーが著したもので、「成長株の選別の考え方と投資の手法」を懇切丁寧に解説した株の指南書です。私がこれまでに読んだ数多くの株式投資関連の書物の中で、間違いなく最高峰の秀作です。
初心者から上級者まで、得るものが多い秀逸な仕上がりになっており、現に私自身も、とても参考になりました。「高成長の業績の裏付けがある企業の株価が上がる」という、成長株の基本中の基本を、とてもわかりやすく説明しています。「当たり前のことを、当たり前のようにして、しっかりやっていける人が成功する」とよく言われますが、本書はまさに、そういったタイプの成功を手にするためのバイブルです。
そして、中でも、四半期利益の増加率を割り出す手法や、「売り圧力レシオ」の発想は圧巻です。しかも、エクセルを用いて、それらを実際に算出してみようとすると、実は意外と手間がかかるのですが、それがまた、とても良いと思うのです。著者自身も本文で述べているように、「すぐには手に入らない情報」だからこそ、他人を一歩リードできるのです。また、少しの手間を惜しんでは、投資では成功しません。
さて一方で、株式投資の方法論を学ぶ際に、強調しておかなければならないことは、「『成長株への投資法』と『割安株への投資法』とは、根源的なところで、その考え方が異なる」ということです。
すなわち、著者は、第2章で「底値買いは報われない」と述べていますし、第4章で「ナンピンは最悪の選択」と述べています。また、本書の随所で、一貫して「損切りの重要性」を強調し、第4章では、「8%下がったら絶対に損切り」と述べています。これらのことは、「成長株への投資法」としては非常に意味のあることで、的を射るものです。成長株への投資を行う場合には、是非とも、本書の指南通りに行動されることが望ましいでしょう。
しかしながら、私自身は「割安株への投資法」を研究する立場にありますので、「底値買い」をして報われた経験を持っていますし、ナンピン戦略も用います。また、「損切り」については、リーマンショック以降、その重要性は非常に高まったと認識していますが、必ずしも「8%下がったら絶対に損切り」が正解にはならないケースも散見されることを確認しています。すなわち、割安株への投資の場合、最初の買い値をかなり低く設定するため、買い値から8%~10%程度下がったところが大底になることも多いのです。
このように、本書は成長株への投資には、最適な基準を明示してくれていますが、「割安株への投資法」の場合は、考え方が大きく異なるということも付言しておきたいと思うのです。しかしながら、このことは、本書の高い価値を揺るがせるものではありません。要するに、自分が「成長株への投資」で成功しようとしているのか、「割安株への投資」で成功しようとしているのかによって、投資哲学は全く異なってくる、ということを念頭に置くことが重要なのです。
本書は、「成長株への投資」を志した個人投資家にとって、極めて有意義な羅針盤となることでしょう。本書は、プロのファンドマネジャーが、成長株への投資哲学を惜しみなく、かつ、とてもわかりやすく開示した、貴重な一冊です。
株式投資で一番儲かるやり方は、強気相場にて、誰もが欲しがる「勝ち組」企業への投資を行ったときです。
このことを、ほとんど投資家は知っているはずです。
ところが、実際の投資においては、安値を待って買い損ねたり、早く売り過ぎたり、天井で飛び付いて大火傷を負ったり、長居して含み益を吹き飛ばしたりで、なかなか上手くはいかないものです。
そういう私も、上昇相場初期の2003年、後の「スター株」であるエン・ジャパンやダヴィンチを仕込んでおきながら、現実の儲けは微々たるものでした。
林則行氏の新刊『伝説のファンドマネージャーが教える株の公式』では、経験の浅い個人投資家でも、大化けする「スター株」でリターンを得られるよう、13のルールが設定されています。
特筆すべきことは「売りの公式」についても言及している点です。丸々1章、50ページ以上に渡って詳細な解説があります。「買い」の説明だけで終わってしまう書籍も少なくない中、著者の「格の違い」を感じました。
なお、ある程度の投資経験を有する中上級者なら、公式に至るプロセスを追っていくのも興味深いです。本書では、プロセスも丁寧に解説してあります。そうした作業によって、応用力もつくでしょうし、公式を自分なりにアレンジすることも可能です。
参考までに、私が本書で気に入った記述を10箇所ほどピックアップしておきます。全般的に、著者から読者に語りかけるように書かれており、最近の本では読後の印象が強く残っています。
- 自分の納得するまで信じないという態度が相場では重要
- 成功するには、大きな損をしないことが大切
- 株は、儲かるときには黙っていても儲かる
- (過去の主役銘柄について)「あの銘柄は大きく上がったなあ」と人の記憶にあるうちは上がらない
- 低PER株の中にスター株は少なく、ほとんどが雑魚銘柄。それでも高PER株よりはまし
- どこまで上がったら売ればいいかという確実な目安はない
- (塩漬け投資に関して)待つことによって株価の上がる合理的な理由はまったくない
- 損切りがいかに重要かについて触れていないのならば、その本は駄本
- 損を早めに確定して次で儲けることを考え、次の投資に資金を振り向けることが大事
- 最もいけない考え方がナンピン
(角山 智 氏)